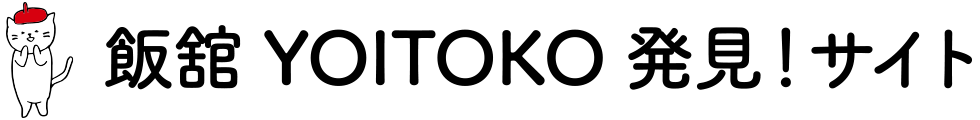本文
更新日:2025年3月25日
草野の三匹獅子(草野)

飯舘村の中心部、草野地区に伝わる風流の三匹獅子舞で、草野の鎮守白山神社の旧暦9月18・19両日の祭礼に奉納されます。また神輿行列にも付き従い、お仮屋などでも奉納しています。しかし、震災以降は中断しています。
獅子頭はイノシシ(猪)、カノシシ(鹿)を意味し、害獣でありながら、山から里に登場する豊穣をもたらす神霊です。この種の獅子舞は、里に豊かさをもたらした獅子が無事山に帰り着くよう、感謝と願いを込めて演ずる芸能ともいえます。
草野の綿津見神社宮司多田家の先祖が記録した棟札には、元文4年(1739年)に白山大明神にこの獅子が奉納されているとありますが、伝承経路などについては明らかではありません。草野地区は旧中村藩領の山中郷に属します。相双地方の風流獅子舞は四人や五人で舞うものが多く、浜通りのそれと似た点もありますが、むしろ中通りの二本松市やその周辺の三匹獅子と類似しており、古い形態を残しているといわれています。中通りと浜通りの中継地点に位置する草野地区は、中通りの文化の影響を色濃く受けていることもうなずけます。風流の獅子舞は会津から中通りを経て、浜通りに伝播し、それにしたがって芸能化も進んだといわれていて、草野の三匹獅子は浜、中の中間の形態を示しています。
前獅子(先獅子)、後獅子の二匹(太郎、次郎ともいう)の雄獅子と一匹の雌獅子で舞い、道化役のひょっとこが加わり、囃子方は笛と太鼓からなります。演目は白扇の舞、歌切り、ざんざこじゃこじゃこ、烏の舞、しだの実拾い、雌獅子かけ、引込みはかの七つで構成されています。