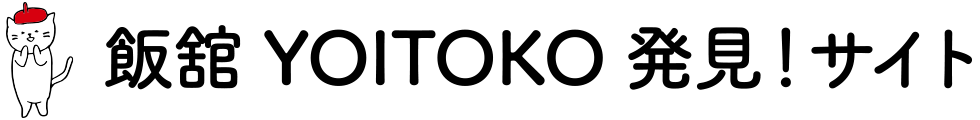本文
更新日:2025年3月25日
作見の井戸(深谷)
深谷地区にある「作見の井戸(さくみのいど)」は、直径0.85メートル、深さ3.6メートルの井戸です。作柄の占い、つまり「作見」に使う井戸であることから、「作見の井戸」と呼ばれています。
二十四節気の「寒(かん)」期間に、井戸の傍にある長さ4メートルほどの尺棒(しゃくぼう)で水深を測り、その時の水の浅深によって作柄を占います。底から2.25メートル(七尺四寸二分)で平年作、2.2メートル(七尺二寸六分)以下なら不作、2.3メートル(七尺五寸九分)以上であれば良作、満水ならば大豊作とされますが、厳密な基準があるわけではなく個人の判断に委ねられます。この結果はその年の作付けの判断基準にする人も多くいました。
伝承では、この井戸は江戸時代末までは某家の屋敷の井戸であったとか、近くの観音様(勢至観音堂)の井戸であったなどといいます。日常的に使われることがなかったため傷みが目立つようになり、昭和五十五年(1980)に深谷地区の有志が井戸枠や周辺を整備し、傍らに小祠や鳥居を設けて新たに作見水神を祀(まつ)り始めました。
寒冷地の飯舘村は冷害などに頻繁に見舞われました。「作占い」は作柄の判断を神霊に委ねる民間信仰ですが、「作見の井戸」は経験の積み重ねによって導き出された民俗知識でもあり、厳しい自然と向き合う暮らしから生まれた生活の知恵ともいえます。