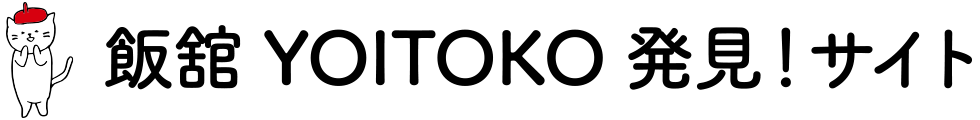本文
更新日:2025年3月25日
比曽の十三佛(比曽)

比曽愛宕神社境内の花崗岩の岩壁に線刻された十三佛は「弘法の爪彫り石」と呼ばれ、地元の人々に崇敬されています。嘉永年間(江戸時代後期)の記録には「壱丈四面(の)大石江(え)十三佛之(の)御姿空海御作申傳」とあり、昔から弘法大師の作との伝承があります。
また、愛宕神社が鎮座する岩壁の上部にも4体の仏が線刻されており、「元禄五壬申年(一六九二)五月」の銘が読みとれます。
なお、この比曽地区にあった東善寺との関連や十三佛信仰との関わりが指摘されてはいますが、誰が、いつ頃、どのような経緯で制作したのか、詳しいことはわかっていません。
【十三佛信仰】
室町時代に生まれた信仰で、死後の世界における心理にかかわる13の裁判官、或いは13回の追善法要(初七日~三十三回忌)を司る13の仏(裁判官の本地仏)を石板や掛け軸にして信仰したもの。特に閻魔王(地蔵菩薩)は広く知られています。