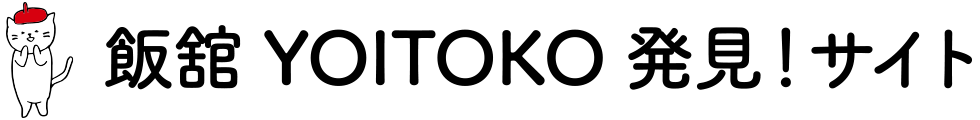本文
更新日:2025年3月25日
比曽の三匹獅子(比曽)
飯舘村比曽(ひそ)地区に伝わる民俗芸能で、二匹の雄獅子と雌獅子一匹の計三匹舞う風流(ふりゅう)系の獅子舞です。相馬地方の風流の獅子舞は獅子頭を被った4人とか5人で舞う例が多いのですが、比曽は中村藩領に位置してはいても、舞の形態から類推すると、隣接する二本松市内や田村郡の三匹獅子とよく似ています。このことからも、中通りの獅子舞の影響を多分に受けているようです。約200年前に伝来したといいますが、詳細は不明です。中村藩主が巡検した折、舞の勇壮さに打たれて藩主相馬家の九曜の紋の使用を許したという伝承もあります。
比曽地区にある田神社、羽山神社、愛宕神社、稲荷神社の祭礼に奉納されていましたが、東日本大震災以降は不定期に演じられています。
雄獅子は先獅子と後獅子、雌獅子を中獅子とよび、「千穂竹」と称するササラ(摺りササラ)と笛、大太鼓の囃子に合わせて舞います。獅子は「ダコダンコキレーロ」で入場し、「トロロ」、「岡崎」、「桝形」と続き「雌獅子奪い」で演目を終えます。
イノシシ(猪)、カノシシ(鹿)などを意味する獅子が山から下り、再び山に戻る姿を表現しています。里人にとっては害獣であると同時に、里の作物の豊穣をもたらしてくれる神ともみなしており、山から里に下りた神霊としての獅子が、無事に山に帰っていただくことを願う風流の芸能です。